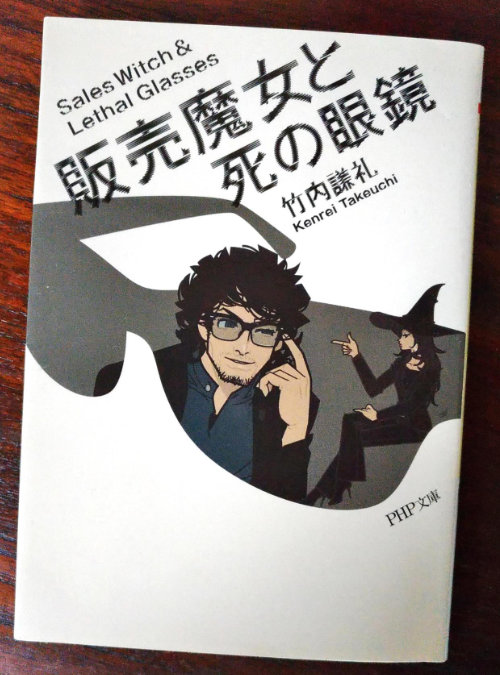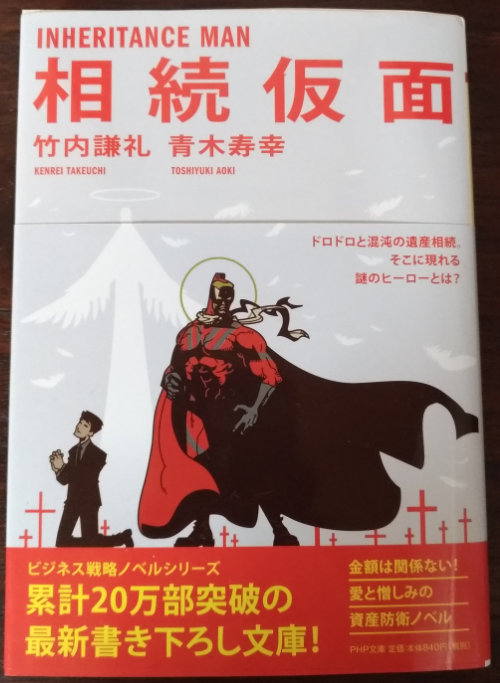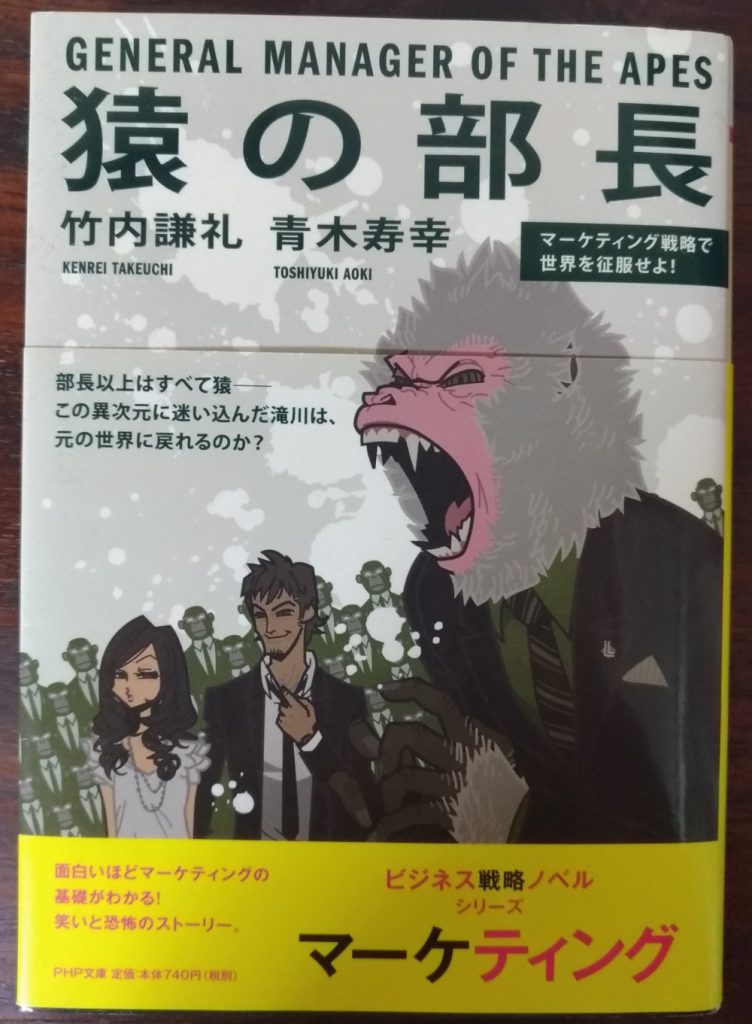30代くらいまでは、自分にとって本といえば小説で、アガサクリスティーや栗本薫などを読んでいたのですが、40代くらいからは小説だと現実から逃避しているような気がしてきました。
また仕事でも、いろいろとこのままでは行き詰まってしまうぞ、という感じがしてきていたので課題解決などのビジネス本をたまに読むようになってきたのですが、Kindleを手に入れてからは、無料で読めるビジネス本をチラチラと読みあさってきました。
そんな中でめずらしく、古本屋さんで買った本が今回ご紹介する森新さんの「アウトルック最速仕事術(ダイヤモンド社)」になります。
いまや誰もがつかっているアウトルック
しばらく諸事情により仕事で別のメールソフトを利用していたのですが、再度、今年の10月からアウトルックを使うことになりました。
しかし、かなり長いブランクがあり使い方をだいぶん忘れていたのですが、そんな中、ちかくの古本屋さんでこの本を見つけました。
チラチラと立ち読み(すみません)していると結構しらないことが書いてあるし、なにより読みやすい(1つのノウハウ毎に数ページずつ使ってわかりやすく書いてある)こともあり、買ってみることにしました。
しかもお値段が元々1,600円くらいだと思うのですが、中古ということで1,200円くらいになっており、さらに帯が無いので?そこから半額になっていました。
リモートワークの通信環境遅延対策に最適!
基本的にはアウトルックで使えるショートカット技が載っていてそれはそれで役になったのですが、個人的にはそれ以外に以下の内容がとても役に立ちました。
1.メール画面の初期表示設定
2.OSコマンドの効率的な呼び出し
1.メール画面の初期表示設定
個人的には、メール画面の構成としては、「メールフォルダ(左)」「受信メールリスト(上)」「メール内容(下)」の3ペイン構成がベストだと思っていました。
しかしこの本では、「メールフォルダ(左)」「メールリスト(中)」「スケジュール(左)」を推奨しています。
私は最初、この推奨は受け入れがたいなあと正直思っていました。これだとメール本文を確認する為に、いちいちメールをひらかなければならないので面倒ではないかと。。
しかし、試しに1度このパターンにしてみたところ、良さがわかってきました。
まず第一に、フォーカスするメールを変えた際に、いちいちメール本文が切り替わらない為、回線状態がよくない私のネット環境にやさしい気がします。
また、かならずしもメールを開かないと内容がわからないかというとそういうわけでもなく、メールリストの表示行を最大の3行にすれば、メールを開かなくても、大体、そのメールが何のメールだったか思い出すことができます。(まあ、初回は開きますが。)
また、開いたあと、いちいち閉じるのがめんどくさくないかという点もありましたが、閉じるのは[ESC]キーを押すだけです。
さらに、そのメールに返信をした時に自動的に元のメールを閉じる設定をしておけば、メールが開きすぎてぐちゃぐちゃになることもありません。
第二に、スケジュール確認の為、画面に切り替える必要が無いというのも大きなメリットです。
この画面の切り替えはショートカットでできるとはいえ、それなりに処理時間がかなります。(たぶん5秒くらいだと思いますが。)これを推奨パターンの画面にしておけば、往復で10秒、毎回時間を短縮することができます。
これは、今、ビデオ会議への参加や自分のスケジュール確認の為にいちいち画面を切り替えている人にとってはとても効率的だと思います。
また、別途、特定の人の組み合わせでスケジュールが空いているか確認したい場合のわざもこの本には書かれていますので、それを組み合わせれば最強に効率的かと思います。
2.OSコマンドの効率的な呼び出し
これはこの本を買ったときには気がついていなかったのですが、OSの[Win]+[R]ショートカットをつかった効率化も目から鱗でした。
もともとこのショートカットを知っていてたまにつかっていたのですが、この本に書かれている発想は正直ありませんでした。
いままでは、このショートカットでExplorerを起動して、それから特定のディレクトリまで移動するといったことをしていたのですが、回線環境がわるい場合、ひとつディレクトリを移動する毎に数秒待つ必要があり(最悪、2、3回くりかえさないと移動してくれないことも)とてもストレスがたまっていました。
しかしこの本でこのショートカットを使ったもっと効率的ななやり方があることに気がつかせてくれました。
もしかしたら、普段何気なくつかっているその他のOS機能の中にも、もっと効率的につかえるものがあるのではないかと気がつかせてくれるものでした。
新品で買っても損なし!(笑
ぜひ皆さんもこの本を買ってみて、隅々まで読んでみてもらえると良いと思います。
自分の会社のなかでは、かなりショートカットを使いこなしていると自負していた自分ですが、こんなに知らなかったことがあるのかと、改めて気がつかせてくれた良い本です。
リンク