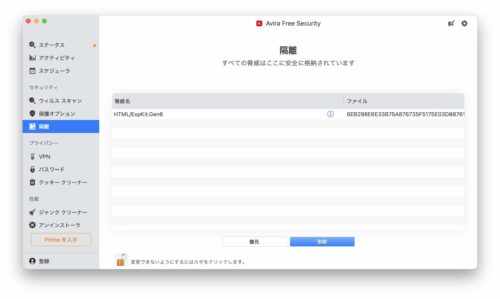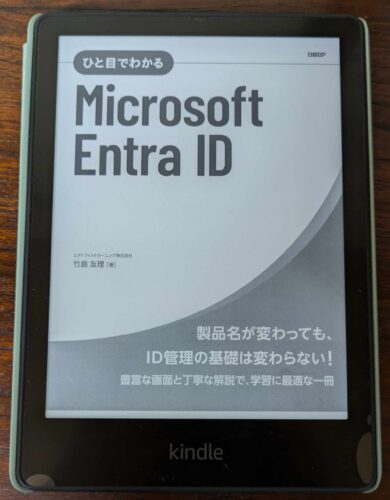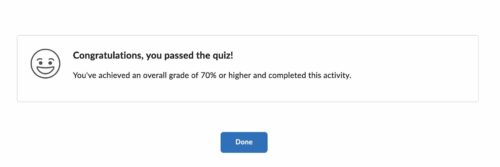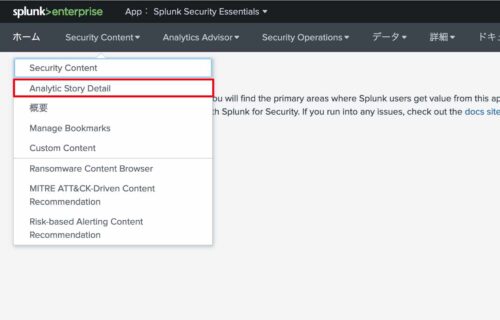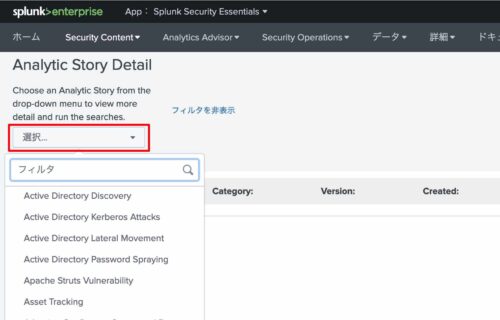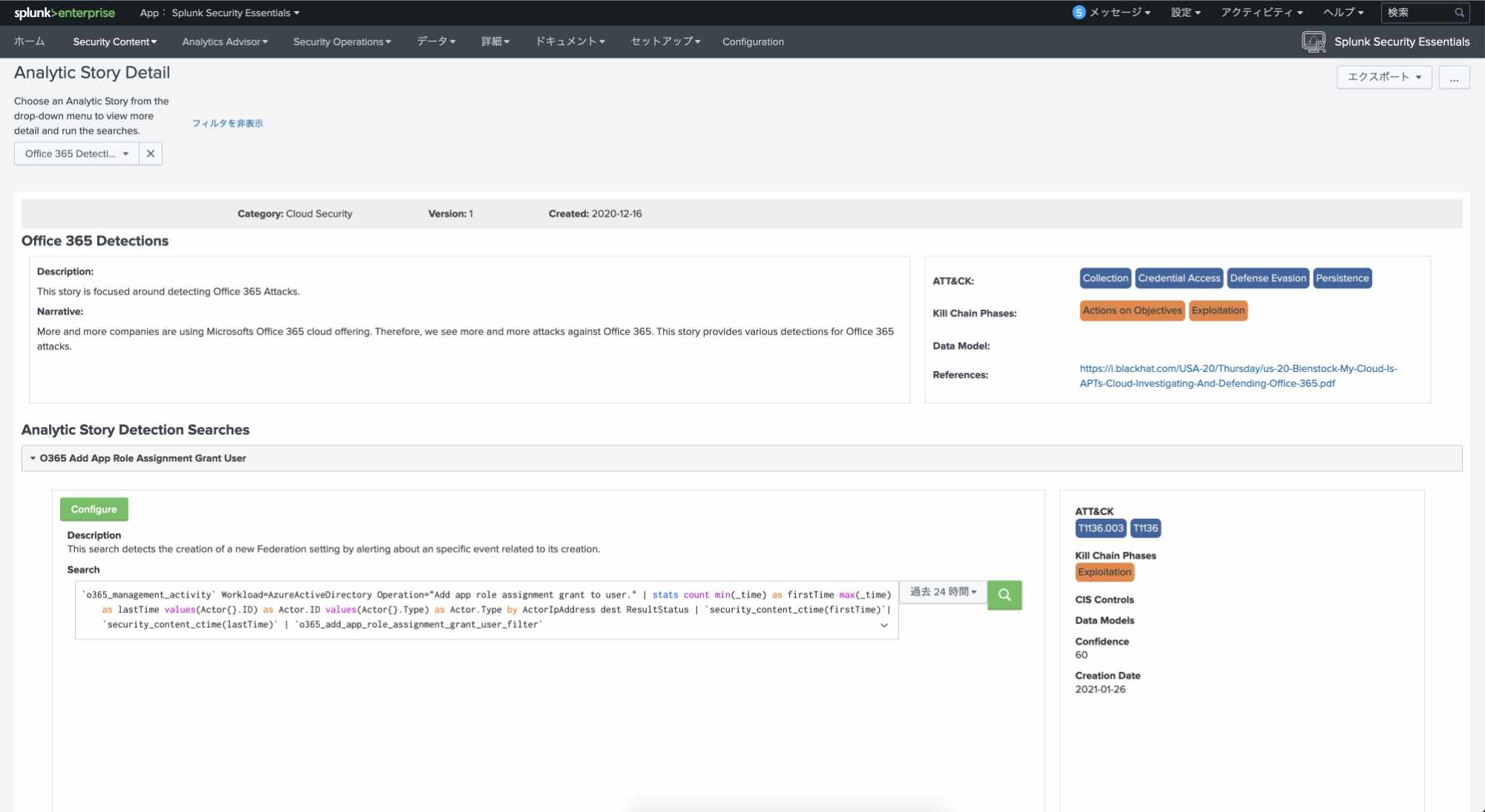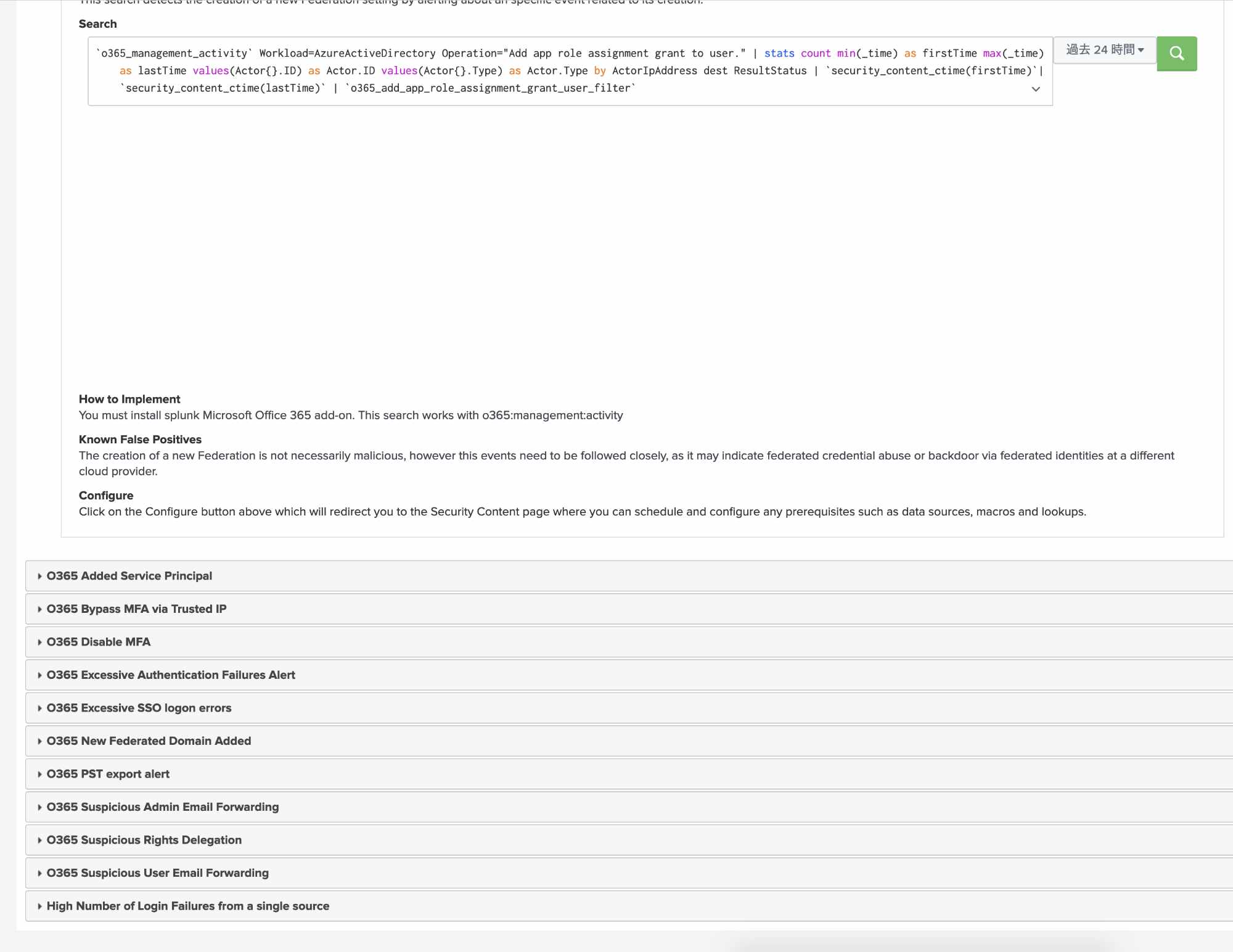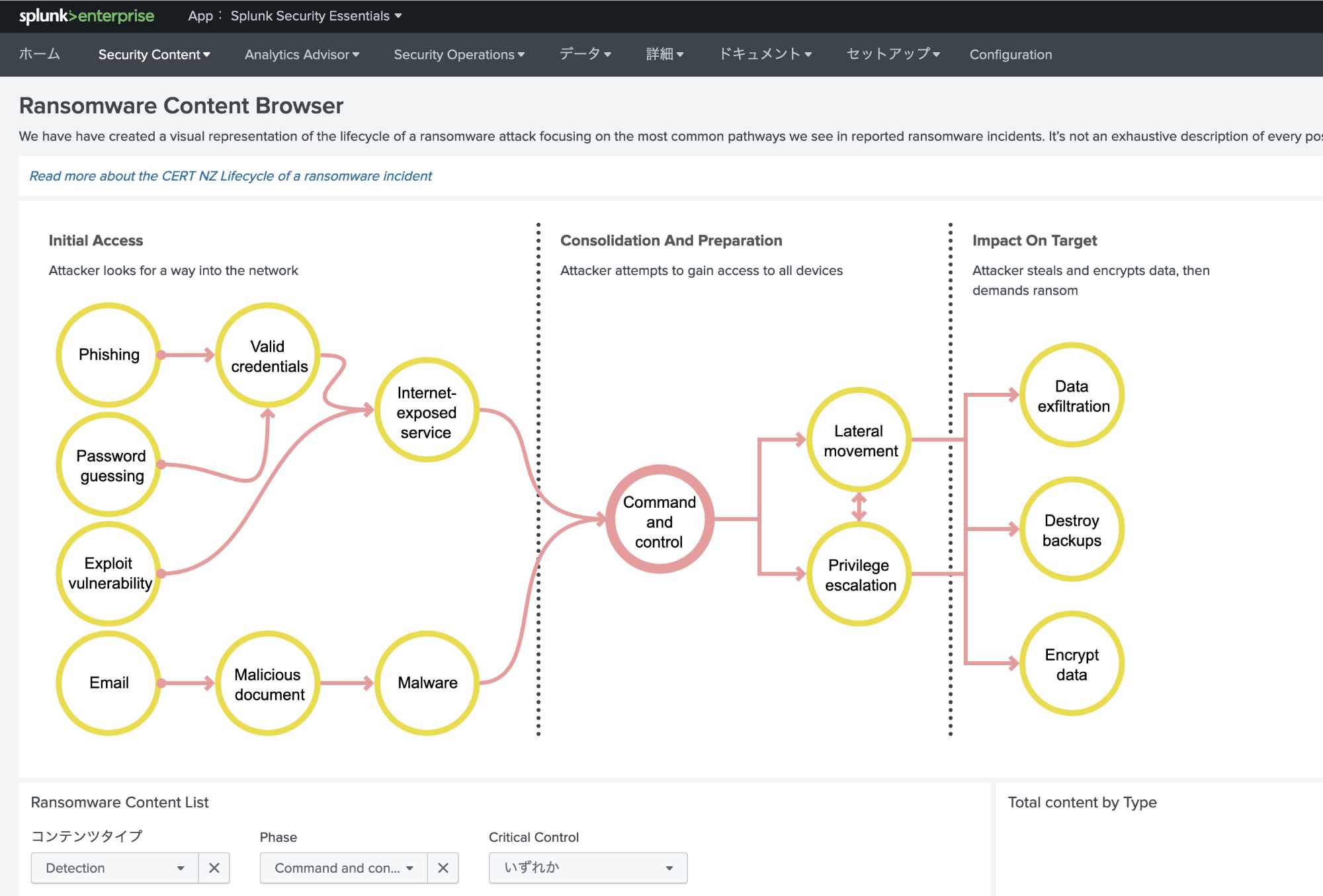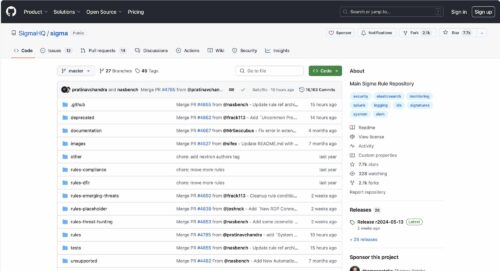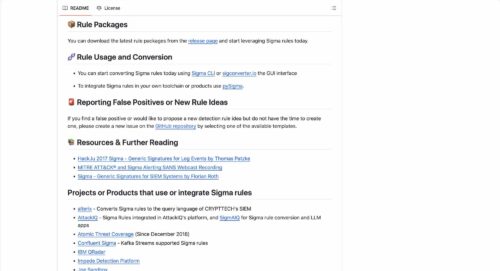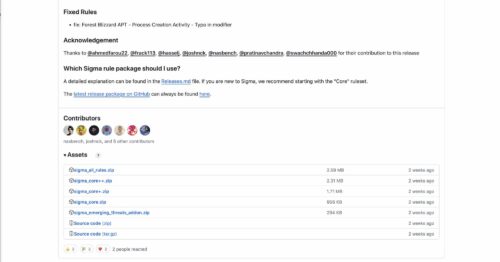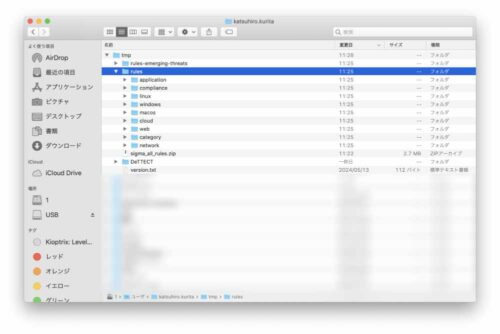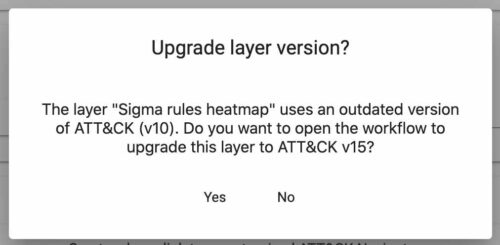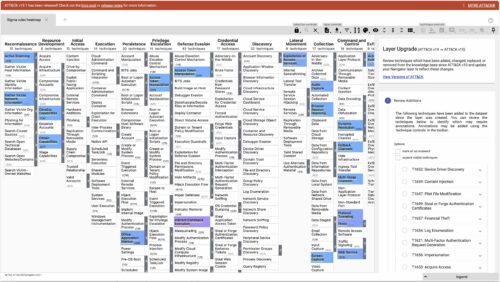2025年10月、Microsoft認定試験 SC-200(Microsoft Security Operations Analyst Associate) に、2回目でようやく合格しましたのでその体験談をここに記載しておきます。
試験の印象と難易度
正直に言うと、SC-200はかなり難しい試験です。
KQLの理解だけでなく、「どの製品のどの機能で何ができるか」を細かく把握する必要があります。
特に難解なのは以下の部分ではないかと思います。
- Security Admin、Owner、Contributorなどの権限違い
- Sentinelのトリガー(Playbook, Automation rule, NRT rule)
- Defender for Servers / Endpoint / Cloud の有効化条件
1回目で不合格だった理由
1回目の受験では、途中まではそこそこ順調に進めていたのですが、途中でそれまで解いた問題の一覧が表示され、その時点で全問解いたと勘違いし問題の見直しをじっくりしてしまいました。
しかしながら実は最後に長文の問題が残っており、それに気づいた時には残り5分をきっていました。
結果、700点まであと14点というところだったので、すべて問題を解き終わっていたら合格していたかもとおもうととてもくやしい思いをしました。
全体で問題数がどれくらいあるのかは、最初に把握しておくことが重要だと思い知らされました。
2回目で合格できたポイント
2回目は、前回の出題内容をしっかり思い出し、弱点を徹底的に潰す学習法に切り替えました。(ただ、1回目と同じ問題はほどんど出なかったように思います。)
その時に実施したことは以下の通りです。
- 1回目の試験結果の紙に自分の弱点が書かれているのでそれを確認
- 特にSecurity for COPILOT はあまり勉強していなかったにもかかわらず結構出題されていたので重点的に勉強
- ExamTopicsで似た問題を反復練習
- ChatGPTで不明点を深掘り(公式ドキュメントもあわせて確認)
結果、問題を見直すことなく時間にも余裕を持って合格できました。合格点はそれでもぎりぎり730点くらいでしたが。。。
ExamTopicsについて 有効度:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
このサイトには過去問題が掲載されており、最も実践的な学習サイトです。私が受けた試験でも、10問以上は同じ問題が出たのではないでしょうか。
一方で、このサイトでは明確な解答は書かれておらず、受験者が正しいと思う答えが投票されているだけので、ChatGPTやMicrosoft Learnで裏付け確認をしながら使うのがコツです。
ExamTopics – SC-200
https://www.examtopics.com/exams/microsoft/sc-200/view
なお、残念ながら現在、無料では最初の10問くらいしか見ることができず、有料契約する場合、月700ドルくらい支払う必要があります。(以前はもっと見れたようですが。)
この支払いをする価値は十分にあると思いますが、このサイトにてクレジット支払いしても大丈夫かどうか正直心配になりました。
ちなみに一瞬だけですが、Googleで以下の通り「サイト指定 sc-200 検索文字列」で検索を行うと、最初の10問以外のSC-200の質問も表示されます。(5秒くらいですが。)
Google 検索例
site:www.examtopics.com sc-200 copilot
ChatGPT 有効度:⭐️⭐️⭐️⭐️
ExamTopicsなどと並行し、ChatGPTに対して正解とその根拠について質問しながら勉強を進めました。
これにより、単純に問題に対する正解を覚えるだけではなく、正解の背景を詳しく確認することができ、理解促進につながったと思います。
最後に
SC-200は決して簡単ではありませんが、1回で受からなくても諦めず、ChatGPT・ExamTopics・Microsoft Learnを組み合わせて勉強すれば、必ず合格できます!